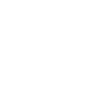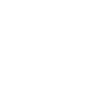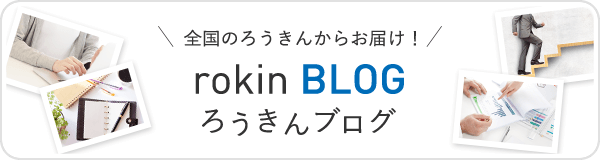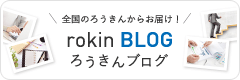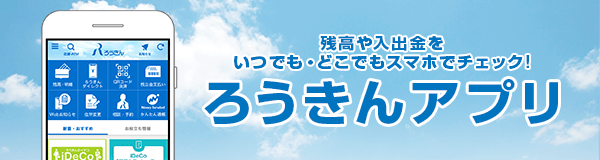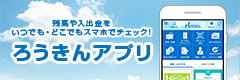労金業態では、IYC2025の期間中、全8回のWEB学習会の開催を予定しています
第5回WEB学習会の開催
2025年8月28日(木)に、第5回WEB学習会を開催しました。本学習会は、〈ろうきん〉で働くすべての役職員の協同組合への知識・意識の向上を図り、「協同組合としてのろうきん」を見つめ直す機会として企画したものです。今回は第5回の学習会の様子をお伝えします。
第5回「労働者自主福祉運動と労働金庫の歴史と役割」
第5回WEB学習会は、中央労福協講師団講師ならびに労金運動推進アドバイザーである高橋 均氏を講師に迎え、「労働者自主福祉運動と労働金庫の歴史と役割」をテーマに、労働金庫の理念や歴史について、労働金庫や中央労福協、生活協同組合との関係性を紐解きながらご説明いただきました。
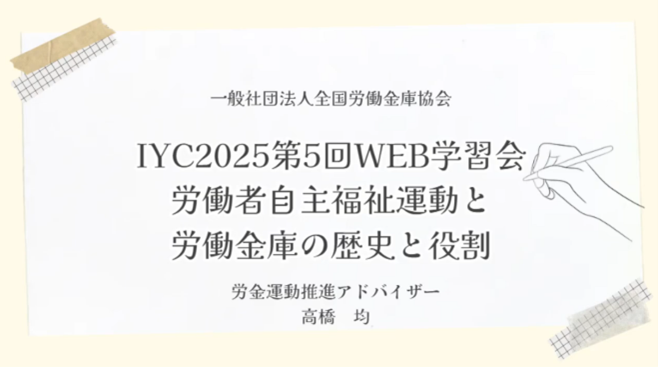
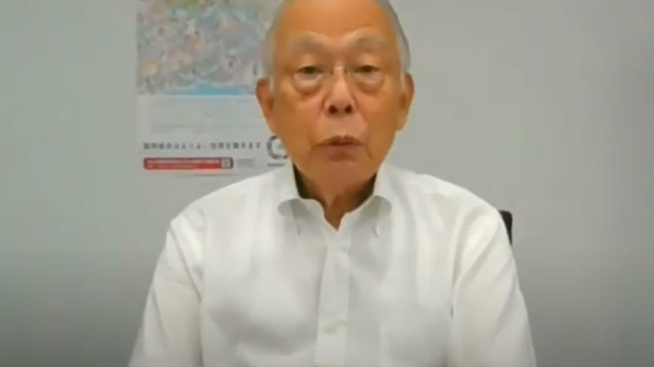
労働金庫や全労済(こくみん共済coop)は労働組合が自主的に作ったものであり、「労働者自主福祉事業・運動」と呼ばれます。
戦後、続々と結成された労働組合が、生活物資の調達のために上部組織の枠を超えて連携し、生活協同組合とともに中央労福協を結成したこと、生活物資の次は質屋と高利貸しからの解放を目指して労働金庫が設立されたこと、さらに新潟大火災では労金からの融資で共済金を全額支払うことができたこと等、労働者自主福祉事業・運動の歴史について順を追ってご説明いただきました。労働金庫ができた当時は、組合員から「労働組合が作った銀行なんか信用できない」と言われ、なかなか預金をしてもらえませんでした。そこで、労働金庫の職員が労働組合の役員と一緒になって、組合員一人一人を説得して歩き回ったそうです。
労働者から預かったお金は、労働者のために使われるため、労働組合と労働金庫・全労済は「客」と「業者」の関係ではなく、「ともに運動する主体」であり、労働金庫の職員として、この関係性を今後も意識し続けていくことが重要であることを学びました。
協同組合は一人一票制で民主的な運営をすること、そして赤字を出さずに事業を継続させること、この二つを両立させるのは非常に難しく爆発的には増えない。これが協同組合の宿命でもあるとのことです。協同組合である労働金庫は、多くの労働者に利用されることにより、今日まで歴史をつなぎ存在していることを改めて実感する貴重な機会となりました。
今後のイベント予定
| 10月22日(水) | 第7回WEB学習会
労金協会政策調査部が進行役となり、「地域を支える温かいお金」をテーマに、ろうきんlabの事例報告と、東北労金・東海労金・近畿労金の各担当者とのトークセッションを行う予定です。
|
| 11月16日(日) | 近畿労金共催シンポジウム
「労働組合と非営利・協同セクターの協同がより良い未来を築く」をテーマに、基調講演、パネル討議を行います。
|
| 11月20日(木) | 第8回WEB学習会
「職域・地域で築くセーフティネット(仮)」をテーマに、静岡労金における高齢者対応の現状について報告する予定です。
|
| 11月28日(金) | 協会主催シンポジウム
学識者や協同組合実践者と、パネル討議を行うことを検討中です。
|
終わりに
今後も2025国際協同組合年(IYC2025)の取組みについて随時発信していきますので、ろうきんブログのチェックをお願いします!